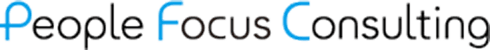お知らせ
2025.06.30(月) お知らせ
■【コラム】組織開発と人材開発の世界から見た着目すべき最近のAIトピック
2025年6月5日に開催されたUMU社とPFC共催のセミナーでは、組織開発や人材開発の観点から、経営リーダーや人事が着目すべき最近の生成AIトピックについて情報提供を行いました。本記事では、その内容を振り返り、考察します。

AIが経営会議に参加する?~生成AIがもたらす経営へのインパクト
生成AIは、顧客行動や取締役会の意思決定に劇的な変化をもたらしています。例えば、SEO(検索エンジン最適化)からGEO(生成AIエンジン最適化)への移行が進んでおり、消費者の8割が検索の少なくとも40%で「AIによる要約」を利用しています。これにより、従来のウェブサイトへのクリック数が25%減少しているそうです。(※出所:“ウェブはSEOから「GEO」へ、ビジネスリーダーのための生成エンジン最適化ガイド” (Forbes JAPAN 公式サイト 2025)
もし自社のビジネスが、こうしたAIが生成する「答え」に含まれていなければ、従来の検索結果で上位にランクしていても、潜在顧客からまったく見つけられない可能性があるということです。
また、取締役会においても、AIを意思決定に取り入れることで、新たな視点が提供され、議論の幅が広がることが確認されています。3タイプのAI介入を設計し、取締役会の議論で以下の観点からAI(ChatGPT)を活用した実験もあります。
- 会議前のアジェンダ分析:議題に対する疑問点や検討事項をAIが提案。
- 会議中のリアルタイム支援:議論中にAIが代替案や分析を提示。
- 意思決定支援:戦略的決断(例:製造拠点の閉鎖、海外進出)に対してAIがメリット・デメリットを整理。
結果としては
- 新たな視点の提供により、議論の幅が広がった。
- 過去に検討されたアイデアの再発見や、意思決定の補強材料として活用された。
等の効果があった一方で以下のような課題があったそうです。
- AIの提案が常に実行可能とは限らず、現場の文脈理解が必要。
- データの質やプロンプト設計に依存するため、導入には工夫が必要。
(出所:「AIを取締役会の意思決定に取り入れる意義とリスク」クリスチャン・スタドラー ,マーティン・リーブス.(ハーバードビジネスレビューオンライン2025年4月29日号)
また、Google Cloudは2025年5月、ビジネスリーダーやマネージャー向けに「Google Cloud Generative AI Leader」という新資格を発表しました。生成AIを活用した業務変革や組織マネジメントが中心で、これまで技術者向けに偏っていたAI学習/資格の対象者を、非技術系にまで広げた点で画期的と言えます。
現時点でのAIと人間の違いはなにか
では、AIにはできなくて、人にはできることは何でしょうか。
まず、AIが苦手とする1点目は、身体を通じた体験からの深い学びです。現在のAIでは、人間の複雑な学習過程を完全には真似できず、特に、身体を通じた経験や、稽古による神経の細やかな変化は、まだAIには難しいと言われています。
私たち人間が記憶し、学習する基本的な仕組みは、繰り返される刺激で神経のつなぎ目(シナプス)を強くするというものです。体を通した経験は抽象的な概念の理解にも役立ちます。たとえば、ヘレン・ケラーの例がよく知られています。
彼女は当初、「コップ」と「水」を区別できませんでしたが、井戸から汲んだ冷たい水が手に触れた瞬間、初めて「water(水)」という概念を理解しました。このように、体を使った経験や感覚は、私たちの知識や技能を単なる情報の集まり以上のものにします。
二つめは本質的な課題の設定です。与えられた問いに対して最適解を出すことには長けているものの、答えのない問題を解くのは苦手です。(参考:『エグゼクティブはなぜ稽古をするのか~ AIでは代替できない“学び”とは?』 梅澤さやか 著)
従業員とAIエージェントが同じ人材プールでマネジメントされる時代に
サイバーエージェント・AIサービス局長 紺屋英洸氏は「いずれAIをヒトと同じように扱うようになる」と語っています。業務遂行に必要なスキルとその「発揮度合」に焦点は絞られ、その主体がヒトであるかどうかは大した問題ではなくなり、「人には、“新しいこと”にチャレンジしてもらい『スキルの移動』を促す」と述べています。ここで言う“新しいこと”とは「プロンプトの設計」を指しています。(出所:「AI時代のリスキリング」(日経ビジネス2025年5月26日号)
AI時代にHRが取り組むべきこと
このような状況のもとでHRは以下のような観点にわけてリスキリングを行っていく必要があります。
- 生成AIそのものに関する知識・スキル
- 生成AIの「使い手」になる(使いこなす)ためのスキル
- 人間にしかできない思考・スキル
現在、4割の人が現在仕事に関するリスキリングを行っていないという調査結果もあります。(出所:「AI時代のリスキリング」(日経ビジネス2025年5月26日号))また、リスキリングに取り組んでいる企業もわずか9%にすぎません。 (出所:「リスキリングに関する企業の意識調査」(帝国データバンク 2024年10月実施)
AIに関するリスキリングを進めていくためには、経営や人事がリスキリングのビジョンを明示し、従業員に対して積極的にリスキリングの機会を提供することが求められます。リスキリングして社員にどんなメリットが生じるのか、企業としてどんな成長が見込めるのか、明確なビジョンを示すことなしに持続的な育成の取組みはおぼつかないといえるでしょう。
生成AIは、組織開発や人材開発の世界にも大きな影響をもたらし始めています。ビジネスリーダーや人事は、率先して生成AIの知識を日々アップデートし、プロンプトの使い手となり、そしてリスキリングの重要性を認識することが求められます。これからのビジネスパーソンは、AIと共存する時代に対応するためのスキル、AIリテラシーを磨いていく必要があります。

松村卓朗
ピープルフォーカス・コンサルティング
代表取締役