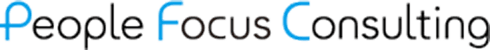コラム
2025.07.31(木) コラム
SDGsやB Corpを“自分ごと”にするカードゲームの力
ゲームで社会課題を“体感”する
こんにちは、サステナビリティ事業推進室長の千葉達也です。
SDGsやB Corpといったサステナビリティに関連する言葉は、今や多くの職場で共有されています。しかし、日常の業務とつなげて語れる人は、まだ多くありません。
「言葉は聞いたことがあるけれど、どこか遠く感じる」
「社会課題って大事だけど、自分の仕事とどう関係あるの?」
そんな一般社員のみなさんの“もやもや”を、体験を通してクリアにしていく手法があります。
それが、カードゲームです。様々な種類がありますが、今回はその中から、「2030SDGs」と、「Be the Change」 のふたつのゲームをご紹介したいと思います。
思考の視野が広がるSDGsカードゲーム
「2030SDGs」は、SDGsの17の目標を達成するために、現在から2030年までの道のりを体験するカードゲームです。
さまざまな価値観や違う目標を持つ人がいる世界で、我々はどうやってSDGsの壮大なビジョンを実現していくのでしょうか。このゲームは「なぜSDGsが私たちの世界に必要なのか」、そして「それがあることによってどんな変化や可能性があるのか」を体験的に理解することができます。
PFCのクライアント企業でも次世代リーダー研修から新人研修まで幅広く導入されており、先日も、6か月間に渡る次世代リーダーシップ研修において、社会課題を解決する新規事業を考える際の入り口にこのSDGsカードゲームを活用しました。参加者はゲームを通じ、SDGsはどんな背景から生まれたのか、企業にとってななぜ利益だけでなく社会課題も一緒に考える必要があるのか、を理解し、新規事業を考える上での思考の枠を広げるために有用な気づきを得ていました。
※カードゲーム「2030SDGs」の紹介はこちら
B Corp認証を疑似体験する「Be the Change -本気になれば社会は変わる- 」
「Be the Change」は参加者がグループごとに架空の会社の一員となり、みんなで協力して、B Corpの認証を目指すゲームです。参加者には、社長、人事部長、広報部長、品質管理部長など様々な役割とプロジェクトカードが割り振られます。役割ごとに異なる視点からプロジェクトの優先順位を話し合い、限られた予算と時間の中で議論や意思決定を行う中で、短期的な成果と長期的なリスク、社会貢献と経済性のバランスなども学んでいくことができます。

組織開発を通じた社会開発への貢献
DEIが目指す姿の実現には、制度をつくるだけではなくお互いの状況を思いやる意識の改革も並行して必要です。PFCでは、これまでにもインクルーシブ・リーダーシップ研修やアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)研修などを通じて、多くの企業のDEI推進を支援してきました。
これからも、自社内でのアクションはもちろんのこと、企業のDEIや組織開発の支援、そして事例やナレッジ共有またその先に続く社会開発への貢献を目指していきたいと思います。
ゲーム体験会のレポート

このゲームはまだ開発中なのですが、先日行われた体験会にいち早く参加してきました。わたしは品質管理・資材調達部長になり、以下のようなプロジェクトカードを配布されました。
・廃棄物量の測定・削減目標の設定
・輸送・梱包資材の見直し重量・容積効率化
・エネルギー使用のモニタリング
・工場内にある指示内容の多言語対応 等
プロジェクトカードはどれも実査にB Corpを取得するのに関連しそうなもので、どこからどう手うとつけるか、優先順位に悩む内容。ふと横を見ると、広報部や法務部の部長役になった人も難しい表情をしていました。カードを見せてもらうと、統合報告書の作成(広報部)やステークホルダーとの対話(法務部)など、重要そうなプロジェクトばかりでした。
次は話し合いです。ゲームの中では、それぞれ役割の中で一番優先順位が高いと思うカードをグループで共有し、話し合って実行する3つのプロジェクトを決めることにしました。
私は悩んだ末に環境への配慮が重要と思い、まずは「廃棄物量の測定・削減目標の設定」のカードを出しました。しかし、他のメンバーから「SBTi認証の取得」というカードが出され、自分のカードよりインパクトの大きいプロジェクトだなと思い、ちょっと後ろ髪を引かれつつ1ターン目のカードを取り下げました。
このような個人視点では最適と思っても、各部署の担当者で集まって話し合うと視点が広がり優先順位が変わる、というのはよくある状況だと感じ、ゲームのはずなのに実際の仕事をしている時と同じような感覚に陥りました。
この後もターンを繰り返しながらB Corp認証の取得を目指していくわけですが、B Corpの内容が自然と学習できることはもちろん、自社でどのように進めていくのが適切か、進める際に注意すべき点などを、具体的に体感することができました。
今回、このゲームを通じて一番感じたことは、この世の中は本当に複雑に絡み合い、影響をし合っているということです。それぞれの役割ごとのプロジェクトカードを出し合った時、自分が担当しているプロジェクトを実行すると、自分にとってメリットがあっても、ある人にとっては負担が大きくなったり想像していなかった影響が与える意見をもらったりします。また、プロジェクトは、短期的には良く思えても長期的にはリスクを増大させることになる可能性もあり、これを時間的、資金的制約がある中で意思決定していく必要があるのは本当に難しいものと改めて感じました。このような正解のない時代だからこそ、どうあるべきかを考える1つの拠り所として注目されているのがB Corpなのかもしれません。
今後、体験会を開催していく予定なので、B Corp認証の取得に限らず、「善い企業とは何か」を考えるきっかけとして興味を持たれた方はぜひご参加ください。
千葉 達也(ちば たつや)
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング
サステナビリティ事業推進室長