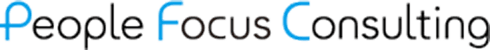コラム
2025.10.03(金) コラム
パーパス研修の現場から見るパーパス浸透設計の秘訣―管理職研修の事例を中心にお届けします
パーパス経営が注目される中、管理職を対象としたパーパス浸透スキルを研修に盛り込む事例が増えています。本記事では、PFCが提供する管理職向けパーパスリーダーシップ研修の実際の様子と、企画・設計で押さえるべきポイントをご紹介します。

「個人のパーパス」はすぐには腹落ちしない
管理職向けパーパスリーダーシップ研修でまず行うのが、「個人のパーパス」の言語化です。研修では様々な仕掛けや演習を経て、2〜3時間かけて丁寧に言語化を進めます。しかし、できあがった自分のパーパスに「しっくりこない」という人もちらほら出てくるのが実情です。
PFCでパーパス関連のプログラム開発を担当するコンサルタントは、「自分のパーパスはこれだ!と最初から確信できる人は極めて少数派。何度も繰り返して内省し、言葉を磨くサイクルこそ大切なんです。4回ぐらいの振り返りで8〜9割の参加者が納得感を得る、というのが私の体感」と言います。
実際、パーパスや理念経営で有名な企業では、リーダーシップ研修で、3か月にわたって5日間、内省を繰り返したり、あるいは管理職の主催で職場でパーパスを語り合うことが習慣化されているなど、「何度も振り返り、言葉を磨くサイクル」が実装・実践されています。
「会社のパーパス」は浸透しているが、経験談が弱い
ある企業では、理念の文言が社員に広く浸透しており、多くの管理職が会社のパーパスを「語る」ことは多くの管理職ができていました。ただし、ホームページに掲載されている内容に準じた、“きれいな言葉”になりがちで、自分の経験談やストーリーを交えて語れる人は少なかったのです。管理職が力強く「自分の言葉で語る」という意味では、真の浸透にはいまだ道半ばといえます。
また、会社のパーパスが個人のパーパスの邪魔をするケースもあります。とりわけ管理職層は、「個人のパーパス」を考える際にどうしても現在の仕事や役割に引きずられてしまいがちです。本来は、「現職や役割に縛られることなく、人生全体での存在意義を考えるべき」なのですが、限られた研修の時間内でそこまでの深掘りを行うことは難しいことが多々あります。
個人および会社のパーパスの探求は「1回やれば終わり」ではなく、定期的な振り返りや組織内での対話の機会を重層的に設計することが大切です。キャリア自律や客観的自己認識の強化に取り組まれている企業では、繰り返しのサイクルを意識した設計が求められます。
管理職だけでなく、部下への展開も視野に
管理職は組織を連結する要であり、パーパス浸透においても要になります。管理職自身のパーパスの言語化はもちろんですが、そこにとどまらず「部下のパーパス言語化を支援できるようになること」にも目を向ける必要があります。自分のパーパスを語れるようになった管理職が、今度は部下との対話を通じて組織全体にパーパスを浸透させる仕組みを作ることで、パーパスの浸透を加速することができます。
パーパス浸透の「4段階」を意識
動画学習が普及したいま、理念を皆で唱和したり、理念が書かれた教科書を輪読するといった教育スタイルは、ほぼ消滅したのではないかと思います。しかしテクノロジーを活用したとしても、単なる知識伝達や、一方通行の教育で終わらないための工夫が依然必要です。
PFCでは、①知っている→②共感する→③行動する→④体現する、というパーパス浸透の4段階モデルに基づいて、パーパス浸透やリーダーシップ開発プログラムを設計しています。
パーパスやバリューズが、コンピテンシーや評価制度に落とし込まれている企業では、浸透が一段と加速化しているのを感じます。日々の職場での対話や上司・部下の1on1、能力開発、エンゲージメント強化の取り組みなど、複数の仕掛けを組み合わせることでも浸透が深化します。社員が定期的にパーパスを見返し、内省する仕組みがあることで、自然と意識が高まっていくのです。
まとめ
パーパス浸透は「一度やれば終わり」ではありません。一過性のイベントだと社員に目されてしまっては、エンゲージメント等へのプラス効果が割り引かれてしまいます。個人のパーパスであれ会社のパーパスであれ、言語化が難しいからこそ、継続的に行い、学習を重ねることに価値があります。
組織全体で「パーパスを語り合う文化」をどう根付かせるかを考えてみてはいかがでしょうか。パーパス浸透のためのモデルやプログラム資料を差し上げています。こちらからお申し込みください。

桑山 政嗣(くわやままさし)
ピープルフォーカス・コンサルティング
執行役員
シニアコンサルタント
プロフィールはこちら