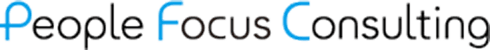クライアント事例
村田機械株式会社・繊維機械事業部様
DEIを堅実に推進するとはどういうことか?
事業部が主導するアンコンシャスバイアス教育と風土改革
事業部が主導するアンコンシャスバイアス教育と風土改革
DEIを自分事に
人的資本経営で多くの企業がDEI(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)へのコミットメントを表明しました。トランプ政権の多様性政策撤廃のあおりを受けないことを切に願うばかりです。一方で、いくら会社として数値目標にコミットしていても、現場レベルでこれまで培われてきた商慣行や風土を変えることは簡単ではありません。意識の高い社員ほど、「うちの会社は対外的にはかっこいいことを言っているけど、職場レベルでは何も変わっていない」と批評家になりがち。かたや管理職は、「業界特有の商慣行には抗っては短期的な成果が犠牲になる」とDEIと業績の板挟みに。管理職や現場リーダーがDEIの社会的・経済的価値を自分事として捉え、DEIを人事から現場主導の取り組みにするにはどうすればよいのでしょうか。
事業部単位でのダイバーシティ推進活動に取り組む村田機械
今年創業90周年を迎える村田機械株式会社は、「革新の分岐点」を掲げ、多様性こそイノベーションの源泉という信念のもと、女性リーダー育成をはじめとする多様性推進に取り組んできました。同社の取り組みの特長は、事業部単位でのダイバーシティ推進活動に継続的に取り組んでおり、事業部のイニシアチブを人事が熱心にサポートし、現場主導の活動を根付かせてきたことです。
売上の大半が海外という事業特性をもつ繊維機械事業部では、今期、事業部のDEI推進活動としてアンコンシャスバイアス教育による風土改革に取り組みました。事業部で企画・推進にあたった事務局の生の声を交えた事例をご紹介し、DEIを人事主導から現場主導にするヒントを探ります。
売上の大半が海外という事業特性をもつ繊維機械事業部では、今期、事業部のDEI推進活動としてアンコンシャスバイアス教育による風土改革に取り組みました。事業部で企画・推進にあたった事務局の生の声を交えた事例をご紹介し、DEIを人事主導から現場主導にするヒントを探ります。
管理職側は考え尽くした!?さらなる進化は少数派の声にある
昨今DEIは国家や政治による揺り戻しに直面していますが、だからこそ企業の役割が大きい側面があります。例えば社会価値と経済価値を両立する企業を認証するBコープは、企業こそが社会の模範としてDEIを実践し、社会変革を牽引すべき存在なのだと主張しています。そのためには、社員に対する継続的なDEI教育の実施、とりわけ、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)に対する教育が、企業がいま行うべきものと位置づけられています。
しかしながら、DEI先進企業であっても、アンコンシャスバイアス教育は社員へのオンライン学習の提供にとどまり、職場風土の改善まで踏み込んでいないのが現状です。オンラインの個人学習は、「人はみな生まれ育った環境から、それぞれ固有のバイアス(偏った見方)を形成する」と社員一人一人の多様性理解を促進します。しかし、「私たちの職場でも、多くの人がもつ無意識のバイアスから疎外感を感じ、力を発揮できない人たちがいる。職場風土をどのように変えていくべきか?」といった、インクルーシブな職場風土づくりを自分ごと化するには至らないのが現状です。
長年にわたってダイバーシティ推進に取り組んできた繊維機械事業部では、今期の活動を検討するにあたり、事業部トップから「管理職だけでこれ以上頭をひねったところで、何も出てこないだろう。DEIをさらに進化させるために、ぜひマイノリティ(少数派)から声を挙げてほしい」という強いリクエストがありました。この鶴の一声に応えて企画されたのが、アンコンシャスバイアス教育と風土改革のワークショップです。
しかしながら、DEI先進企業であっても、アンコンシャスバイアス教育は社員へのオンライン学習の提供にとどまり、職場風土の改善まで踏み込んでいないのが現状です。オンラインの個人学習は、「人はみな生まれ育った環境から、それぞれ固有のバイアス(偏った見方)を形成する」と社員一人一人の多様性理解を促進します。しかし、「私たちの職場でも、多くの人がもつ無意識のバイアスから疎外感を感じ、力を発揮できない人たちがいる。職場風土をどのように変えていくべきか?」といった、インクルーシブな職場風土づくりを自分ごと化するには至らないのが現状です。
長年にわたってダイバーシティ推進に取り組んできた繊維機械事業部では、今期の活動を検討するにあたり、事業部トップから「管理職だけでこれ以上頭をひねったところで、何も出てこないだろう。DEIをさらに進化させるために、ぜひマイノリティ(少数派)から声を挙げてほしい」という強いリクエストがありました。この鶴の一声に応えて企画されたのが、アンコンシャスバイアス教育と風土改革のワークショップです。
女性リーダーのファシリテートで職場のアンコンシャスバイアスに向き合う
職場風土の改善を目指すPFCのアンコンシャスバイアス研修は、次の3部構成になっています。
① アンコンシャスバイアスについて各人が学習する(オンライン個人学習)
② 職場のバイアス事例について各人がアンケートに回答する(バイアス事例収集)
③ アンケート結果レポートに基づいて、ワークショップで話し合う(職場風土の改善)
繊維機械事業部では①②の実施後、③では事業部の管理職約30名と全女性社員約70名が集まり、2度に分けて職場風土の改善を目指すワークショップを実施しました。
このアンコンシャスバイアス・ワークショップにおいて、小グループディスカッションのテーブル・ファシリテーターとして活躍したのが、同社が長年にわたって継続実施している女性リーダー研修(WLP: Women Leadership Program)の卒業生たちです。WLPでは長年にわたり、リーダーシップ発揮の具体的スキルの一つ、ファシリテーション・スキル開発を重視してきました。同事業部に所属する合計15名のWLP卒業生は、存分にスキルを発揮し、見事に各テーブル・グループの対話をファシリテートしてくれました。その結果、アンコンシャスバイアス・ワークショップは次のような成果を生みました。
・女性社員と管理職がアンケートに寄せられたバイアス事例に真摯に向き合い、
・安心・安全な場づくりのもと、日ごろの想いや気持ち、考えを本音で共有し、
・無意識であることや、過剰なやさしさが個人や組織に及ぼす影響を探求し、
・理解を深めた上で、事業部として改善すべき6つの領域を特定することができました。
6つの領域はいずれも、いま企業が組織として向き合うべきDEI領域であり、改善すれば女性社員のみならず全社員にメリットが波及するであろう重要なテーマでした。一つだけご紹介すると、事業部の花形である海外赴任や海外出張機会の公平化、言い換えると、ライフイベントへの過剰な配慮や決めつけをいかに改善し、海外赴任や出張という成長機会のジェンダー平等を図っていくかという課題です。6つの領域は、WLP卒業生がテーマリーダーとして改善提案を取りまとめ、事業部経営層に提案。討議を重ねた上で、DEI活動、人事施策の実践、事業部の風土改革等、しかるべき活動で落とし込まれることになりました。
① アンコンシャスバイアスについて各人が学習する(オンライン個人学習)
② 職場のバイアス事例について各人がアンケートに回答する(バイアス事例収集)
③ アンケート結果レポートに基づいて、ワークショップで話し合う(職場風土の改善)
繊維機械事業部では①②の実施後、③では事業部の管理職約30名と全女性社員約70名が集まり、2度に分けて職場風土の改善を目指すワークショップを実施しました。
このアンコンシャスバイアス・ワークショップにおいて、小グループディスカッションのテーブル・ファシリテーターとして活躍したのが、同社が長年にわたって継続実施している女性リーダー研修(WLP: Women Leadership Program)の卒業生たちです。WLPでは長年にわたり、リーダーシップ発揮の具体的スキルの一つ、ファシリテーション・スキル開発を重視してきました。同事業部に所属する合計15名のWLP卒業生は、存分にスキルを発揮し、見事に各テーブル・グループの対話をファシリテートしてくれました。その結果、アンコンシャスバイアス・ワークショップは次のような成果を生みました。
・女性社員と管理職がアンケートに寄せられたバイアス事例に真摯に向き合い、
・安心・安全な場づくりのもと、日ごろの想いや気持ち、考えを本音で共有し、
・無意識であることや、過剰なやさしさが個人や組織に及ぼす影響を探求し、
・理解を深めた上で、事業部として改善すべき6つの領域を特定することができました。
6つの領域はいずれも、いま企業が組織として向き合うべきDEI領域であり、改善すれば女性社員のみならず全社員にメリットが波及するであろう重要なテーマでした。一つだけご紹介すると、事業部の花形である海外赴任や海外出張機会の公平化、言い換えると、ライフイベントへの過剰な配慮や決めつけをいかに改善し、海外赴任や出張という成長機会のジェンダー平等を図っていくかという課題です。6つの領域は、WLP卒業生がテーマリーダーとして改善提案を取りまとめ、事業部経営層に提案。討議を重ねた上で、DEI活動、人事施策の実践、事業部の風土改革等、しかるべき活動で落とし込まれることになりました。
事務局の皆さんにお聞きしました
「少数派の声を聴こう」という事業部長の鶴の一声を活かすも殺すも事務局次第でありましょう。ここからは、先進性と堅実さ両立の舞台裏、企画推進を担った事務局のインタビューをお届けします。

右から、大谷氏、田桐氏、大橋氏、PFC山田
・同 技術サービス部課長 大谷 昭洋氏(DEI推進リーダー)
・同 デジタル革新室室長 田桐千津子氏(WLP一期卒業生)
事業部の管理職でもあるお三方は、アンコンシャスバイアス・ワークショップに参加者として参画もされました。インタビュアーは、リード・コンサルタントを務めた山田奈緒子(ピープルフォーカス・コンサルティング取締役)です。

お話を聞かせていただいた皆さん
・繊維機械事業部 事業計画部長 大橋 真太郎 氏・同 技術サービス部課長 大谷 昭洋氏(DEI推進リーダー)
・同 デジタル革新室室長 田桐千津子氏(WLP一期卒業生)
事業部の管理職でもあるお三方は、アンコンシャスバイアス・ワークショップに参加者として参画もされました。インタビュアーは、リード・コンサルタントを務めた山田奈緒子(ピープルフォーカス・コンサルティング取締役)です。
Q. アンコンシャスバイアスに正面から向き合って風土改善を試みるという、先進的かつ堅実な取り組みに着手しました。企画当初の心境や思い入れを教えてください。
田桐氏 ようやく私がやりたいことやれるスタート地点に立ったかな、という感じがしました。コロナ前頃から、皆がイキイキ働く職場風土づくりのために、スマイル・カフェという職場横断的な対話の場を作ってきました。ただ、皆が話しやすいことを優先すると、核心に触れるような、とりわけジェンダーバイアスのテーマにはまだ踏み込めなかった。今回、本当にやりたかったことの入り口にようやく立てたなと思いました。「ジェンダー」とつくと、どうしてもちょっとアレルギーありますよね(笑)。
大谷氏 事業部の第5期D&I推進リーダーになった時、DEIの女性メンバーから「他事業部がやっているような女性活躍、ジェンダーに関しての取り組みをうちでもやりたい」と声が上がって、他の事業部をヒアリングしたんです。そうしたら、やっているけれどもなかなかうまく行かない。一過性で終わりがちで継続が難しい、とのことでした。それで、繊維機械事業部では、管理職だけ、女性だけと別々ではなく、一緒にやりたいと思いまして。管理職のメンバーと女性がもうちょっと率直に話ができたらいいなというのが当初の想いです。今回のワークショップに参加者として参加して、そういう雰囲気になったなと思います。また、これまでそういう環境を作ってきたことが実ってきたと感じました。
実は反対意見も結構あって、男性社員から「何で女性だけなの?男でも困っている者がおる」とか、女性社員からも「なんで女性だけ?大多数である一般職男性社員も含めるべきだ」と言われました。それはその通りですが、敢えて、そういった声は受け止めるに留めて、事業部長方針でもある、「具体的にジェンダーに切り込んでほしい」という女性からの声に立ち戻りました。それで段階的に、管理職と女性社員の対話へと進めることにしました。
大橋氏 私は事業部全体のエンゲージメント向上を担当していて、中堅、若手のワークショップ、1on1を推進してきました。女性活躍はD&Iに任せていたのですが、風土改革であり管理職の関わりが重要になってきたので連携しています。
企画当初は、WLPが中心になって女性社員のみで行うような発想でいたのですが、管理職と女性全員、総勢100名となり、2回に分けても50名のワークショップがうまく行くのかどうか、正直疑問でした。そういう意味では、今回の肝はWLPの活躍ですね。女性リーダーが育っていたから、これを活用するというのがうまい建て付けでした。事業部の中に、議論をまとめる手腕のある女性リーダーがこれほど存在するということを示すことができました。
大谷氏 事業部の第5期D&I推進リーダーになった時、DEIの女性メンバーから「他事業部がやっているような女性活躍、ジェンダーに関しての取り組みをうちでもやりたい」と声が上がって、他の事業部をヒアリングしたんです。そうしたら、やっているけれどもなかなかうまく行かない。一過性で終わりがちで継続が難しい、とのことでした。それで、繊維機械事業部では、管理職だけ、女性だけと別々ではなく、一緒にやりたいと思いまして。管理職のメンバーと女性がもうちょっと率直に話ができたらいいなというのが当初の想いです。今回のワークショップに参加者として参加して、そういう雰囲気になったなと思います。また、これまでそういう環境を作ってきたことが実ってきたと感じました。
実は反対意見も結構あって、男性社員から「何で女性だけなの?男でも困っている者がおる」とか、女性社員からも「なんで女性だけ?大多数である一般職男性社員も含めるべきだ」と言われました。それはその通りですが、敢えて、そういった声は受け止めるに留めて、事業部長方針でもある、「具体的にジェンダーに切り込んでほしい」という女性からの声に立ち戻りました。それで段階的に、管理職と女性社員の対話へと進めることにしました。
大橋氏 私は事業部全体のエンゲージメント向上を担当していて、中堅、若手のワークショップ、1on1を推進してきました。女性活躍はD&Iに任せていたのですが、風土改革であり管理職の関わりが重要になってきたので連携しています。
企画当初は、WLPが中心になって女性社員のみで行うような発想でいたのですが、管理職と女性全員、総勢100名となり、2回に分けても50名のワークショップがうまく行くのかどうか、正直疑問でした。そういう意味では、今回の肝はWLPの活躍ですね。女性リーダーが育っていたから、これを活用するというのがうまい建て付けでした。事業部の中に、議論をまとめる手腕のある女性リーダーがこれほど存在するということを示すことができました。
Q. みなさん、管理職としてワークショップに参加もいただきました。アンコンシャスバイアス事例や話し合いで印象に残ったことを教えてください。
大橋氏 入社一年目の女性が、「私こう見えて、思ってることがいっぱいあります」と言って話し始めたのがすごく印象的でした。「キャリアで中途入社した男性がすぐに海外出張に行かれるのに、私は半年以上研修中で、お客さんの顔も知らないで営業してるんですよ」って。彼女の上長は、当然ながら、未来永劫彼女を海外出張に行かせないつもりなんてありません。そして上司部下は近くに座ってるのですが、声は届いてないんだなあ、っていうのに気づかされた出来事でした。私はワークショップ中はずっと傾聴していました。
大谷氏 アンケート結果から、想定以上というか、我々が思っている以上に、女性社員は困ってるんだな、言いたいことが言えないんだな、という印象を受けました。そういう意味では、ワークショップの場では、管理職側は否定的な意見は言わないし、傾聴ができていました。いろいろと研修をやってきた成果です。女性参加者は話しやすかったと思います。
それでも印象的だったのが女性たちの「まだ上司はわかってない」という感覚です。まだまだ我々がわかりきっていない、理解できていないところがあるのでしょう。象徴的だったのが、グループ討議後に男性管理職が気づきを共有した際、ある女性が、いやいやわかってほしいのはそこじゃないんですと、フォーカスしてほしい論点を提示した場面がありました。こんなふうに、職場で臆せず対話できるようにならなければいけない。互いの立場から風景を眺めて、改善すべきところを見据えて改善する、というようなDEIの目指すべき組織像が垣間見えました。
田桐氏 私はアンケート結果の女性側のコメントから、普段は言葉にすることがなく、表面的にはおそらく控えめにしていても、はらわた煮えくりかえってる人もいる、という驚きがありました。片や管理職側のアンケート回答の中に、「アンコンシャスバイアスは自分の職場にはない」というコメントも複数ありDEI教育は継続的にやっていかなければいけないとつくづく感じました。
ワークショップの感想は、やっぱりWLPメンバーすごい!に尽きます。私もWLP卒業生ですが、今回管理職という立場で参加者として参加して、みな本音で話すのはよいのだけど、とりとめのない雰囲気になってきてしまって大丈夫かな?と思っていたところ、ファシリテーターが最後にびしっと意見と論点をまとめてくれて感心しました。ファシリテーション・スキルがすごい。ファシリテーター自身、女性リーダーとしてジェンダー平等に対する課題意識が高いため、論点をうまく捕まえる力があるんだと思います。また、日ごろ仕事でもファシリテーションを活用しているからだと思います。
大谷氏 アンケート結果から、想定以上というか、我々が思っている以上に、女性社員は困ってるんだな、言いたいことが言えないんだな、という印象を受けました。そういう意味では、ワークショップの場では、管理職側は否定的な意見は言わないし、傾聴ができていました。いろいろと研修をやってきた成果です。女性参加者は話しやすかったと思います。
それでも印象的だったのが女性たちの「まだ上司はわかってない」という感覚です。まだまだ我々がわかりきっていない、理解できていないところがあるのでしょう。象徴的だったのが、グループ討議後に男性管理職が気づきを共有した際、ある女性が、いやいやわかってほしいのはそこじゃないんですと、フォーカスしてほしい論点を提示した場面がありました。こんなふうに、職場で臆せず対話できるようにならなければいけない。互いの立場から風景を眺めて、改善すべきところを見据えて改善する、というようなDEIの目指すべき組織像が垣間見えました。
田桐氏 私はアンケート結果の女性側のコメントから、普段は言葉にすることがなく、表面的にはおそらく控えめにしていても、はらわた煮えくりかえってる人もいる、という驚きがありました。片や管理職側のアンケート回答の中に、「アンコンシャスバイアスは自分の職場にはない」というコメントも複数ありDEI教育は継続的にやっていかなければいけないとつくづく感じました。
ワークショップの感想は、やっぱりWLPメンバーすごい!に尽きます。私もWLP卒業生ですが、今回管理職という立場で参加者として参加して、みな本音で話すのはよいのだけど、とりとめのない雰囲気になってきてしまって大丈夫かな?と思っていたところ、ファシリテーターが最後にびしっと意見と論点をまとめてくれて感心しました。ファシリテーション・スキルがすごい。ファシリテーター自身、女性リーダーとしてジェンダー平等に対する課題意識が高いため、論点をうまく捕まえる力があるんだと思います。また、日ごろ仕事でもファシリテーションを活用しているからだと思います。
Q. 今回の取り組みを経て、自組織のDEI推進についてわかったことや学んだことを教えてください。
大橋氏 管理職やリーダーを目指す以外の、多様なキャリアがあっていいということに、結構悩んでいる人がいるということ。ジェンダーに関わらず、優秀な人、成果を上げる人、意欲がある人、意思表明をする人は、どんどん引き上げる風土はあると思います。他方、目立たない人たちのキャリアの在り方を豊かにしていくことが、組織としてこれからジェンダーを超えた大きなテーマになるだろうと感じました。
大谷氏 今回、ジェンダー平等の切り口でしたが、出てきた課題や打ち手は、若手でもベテランでも誰でも、職場でエンゲージメントについて対話したら多分同じような課題が出るのだろうと思います。どこの職場でも活かせると思います。ということを管理職みなに気づいてほしいと思いますが、それはこれからだろうな…
大谷氏 今回、ジェンダー平等の切り口でしたが、出てきた課題や打ち手は、若手でもベテランでも誰でも、職場でエンゲージメントについて対話したら多分同じような課題が出るのだろうと思います。どこの職場でも活かせると思います。ということを管理職みなに気づいてほしいと思いますが、それはこれからだろうな…
Q. 事業部のDEIの今後の展望は?
大橋氏 今回のジェンダー教育は、はじめの一歩だと思います。ワークショップである女性が、育児の経験を上司は知らないと、言いましたが本当にそのとおりで、僕ちょっと刺さりました。身近な人の体験談として知る機会があると非常に刺さるだろうと思いました。同じ部署のワーキングマザーの一日から、生産性の高い働き方を考察する、といったことをやってみたい。
大谷氏 今回の取り組みで、管理職をこちらの方に取り込めたのは大きいと思います。やっぱりみんなが自分事にして、自分が風土を変えなきゃいけないことに気づいたというか、少し理解していただけたのかなと。自分は男性であるがゆえに、昇格や昇進、日々の成長機会などで不利益を被ったことはない、ということをすごく思いました。女性は逆で、女性であるがゆえの不利益が思いのほか多いことに、今回リアルに気づきました。
田桐氏 今期から社内の呼称がD&IからDEIに変わります。まだE(エクイティ・公平性)の意味が何かわかってない人も多く、管理職クラスでも女性に対する施策は「不公平」と思っている人もいる。企業組織の中で男性、正社員であるだけで特権階級にあって、女性であるだけで不公平があることに気づいてないんです。今後はエクイティの理解浸透が必要だと思っています。
大谷氏 今回の取り組みで、管理職をこちらの方に取り込めたのは大きいと思います。やっぱりみんなが自分事にして、自分が風土を変えなきゃいけないことに気づいたというか、少し理解していただけたのかなと。自分は男性であるがゆえに、昇格や昇進、日々の成長機会などで不利益を被ったことはない、ということをすごく思いました。女性は逆で、女性であるがゆえの不利益が思いのほか多いことに、今回リアルに気づきました。
田桐氏 今期から社内の呼称がD&IからDEIに変わります。まだE(エクイティ・公平性)の意味が何かわかってない人も多く、管理職クラスでも女性に対する施策は「不公平」と思っている人もいる。企業組織の中で男性、正社員であるだけで特権階級にあって、女性であるだけで不公平があることに気づいてないんです。今後はエクイティの理解浸透が必要だと思っています。
PFC山田 いまDEIに取り組んでいる他社の人事や事業部の方々にとって、たいへん参考になるお話をありがとうございました。私はWLP第1期の講師でしたから、第1期の田桐さんはじめ、WLP卒業生と力を合わせてアンコンシャスバイアス教育と風土改革に挑戦できて、こんなに嬉しいことはありませんでした。WLP卒業生が率直に話し合う場をつくり、アウトプットを言語化していく姿を目の当たりにして、ファシリテイティブなリーダーがインクルーシブな組織の扉を開くという確証を得ました。
事務局の皆様がPFCを事務局チームの一員として迎えてくださり、組織観、課題意識、やりたいことを明確に共有くださったことに感謝いたします。事務局はまた、熱い想いをもってスポンサーシップを発揮し、WLP卒業生をエンパワーし、一参加者としては自ら学ぶロールモデルとなっておられました。これらはまさに、変革リーダーに求められる行動です。試行錯誤しながらも、事務局が学びを楽しみながら変革リーダーシップを発揮すると、組織の風土改革は走り出すのだと改めて実感しました。