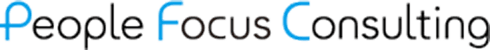コラム
2013.03.31(日) コラム
サッカーから学ぶ組織開発・人材開発 22:日本サッカー “アマからプロへ”の大変革(2)
【サッカーから学ぶ組織開発・人材開発(松村卓朗)】
第22回: 日本サッカー “アマからプロへ”の大変革~誕生から20年経ったJリーグ~(2)
世の中のほとんどの変革は、この第1ステップ「変革の危機意識の醸成」で躓いている。つまり、変革が始まりすらしないということだ。危機意識の醸成とは、“今のままでも何とかなるだろう”という空気を変え、人々を“このままではいても立ってもいられない”という状況にさせることだ。
Jリーグを生み出すことにつながった、川淵氏が抱いた危機感はどのようなもので、どのように周囲の危機意識を醸成していったのか。
調べてみると、川淵氏が抱いた危機感は、いつもは閑古鳥が鳴いていた日本リーグの試合にあるとき4万人を超える観客を集めた試合があり、このときにさらに高まったという。ちょっとした成功を収めたときに、さらに危機感が増したという意識の持ち方が、私には実に興味深かった。
『第2次活性化委員会をスタートさせるとともに着手したのが、“国立競技場を満員にするプロジェクト”である。日本リーグのある試合に、満員の観客を呼ぼうという試みだった。僕が旗を振り、関東近辺のサッカースクールの指導者に「日本のサッカーを応援するために集まってほしい」という手紙を大量に出すなど、宣伝に努めた。その結果満員といかないまでも、それまでJSLでは入ったことのない42000人というファンが集まった。当時としては珍しく、マスコミにまで注目された。
しかし、僕には達成感など全くなかった。肝心の試合が面白くなかったからだ。ただボールを蹴り合うばかりで厳しさが微塵も感じられない。「誰がこんな試合にカネを払って見にくるものか。一日だけ満杯にしても何の意味もない。もっと大きく何かを変えなければならない」と思った。心の底から、日本のサッカーの現状というものに飽き飽きした。
このときの僕には、観客を呼ぶために考えられる限りのことをしたという思いがあった。素晴らしい芝生のグラウンドを準備し、昼間よりもスピード感があって少しでも試合をおもしろく感じられるようにと考えてナイトゲームを試みた。しかし、肝心のサッカー自体を面白くすることはできなかった。
それ以前にも、釜本邦茂のヌードをポスターにするなどさまざまなアイデアを出してはいた。確かにある程度のインパクトはあったかもしれない。でも、そんな小手先の手段をいくら施しても「日本サッカーの本質から見直さなければ、何も変えられない」ということが分かった。
浮かび上がったのが「アマチュアの限界」という現実だった。当時プロ契約を結んでいる選手はいたが、厳しいことを言えばそれは単なる形だけの話だった。例えば当時日本代表選手を集めて50Mダッシュを10本行ったら、「走り切れ」「サボるな」「途中でやめるな」と全員を怒らなければならない始末だった。ところが、アーセナルに視察に行ったとき、16歳のプロになるかならないかという間際の子どもに50Mダッシュを試みると、コーチのやることは単に笛を吹くだけ。何も言わなくてもみんな必死で走り切る。
これこそがプロとアマの差だ。その溝を埋めないまま練習を続けていたら、日本と世界の差は開く一方。「うまくならないとクビになる」という状況に追い込まない限り、日本のサッカーは変わるはずもない。人間は弱いから、会社員という二足の草鞋を続けていると、サッカーで躓いたら「サッカーはともかく仕事はできる」と、問題に真正面には立ち向かわずに逃げてしまいかねない。日本サッカーを強くするには、プロ化以外に道は考えられなかった。』(出所:「日本サッカーが世界一になる日」NHK知るを楽しむ2006年5月8日放送内容を加筆修正)
さらに、自身が抱いた危機感を周囲に共有していかねばならないが、その方法として、川淵氏はプロ野球の現状を反面教師として徹底的に活用していたということが、印象に残っている。例えば、日本のプロ野球のガバナンスのなさ、オープンネスの弱さが、何かあったときにはファンや選手の乖離を招くのだという危機感を共有して、Jリーグは徹底的にオープンにしなければならないという方向に導いている。
ちょうど当時は、近鉄・バファローズが経営悪化で、オリックス・ブレーズスと合併するということが世間の話題をさらっていた。近鉄・バファローズの経営陣が、「合併は選手の意向を聞いてやるものではない」という趣旨のことを言って、選手やファンとの溝を深めていた。
私も、合併は選手の意向を聞いて行うものではないというのは、確かにその通りだとは思ったし、会社が赤字では球団経営が続けられないということは、選手やファンでは如何ともしがたいことだとも思ったものの、とても違和感があった。近鉄は、「30億円の赤字だ」というけれども、根拠となる数字を一切示そうとしなかったからだ。球団は「経営を続けられない」と言い、選手は「何とか続けてほしい」と言うなら、例えば球団が自立するまでの道筋を、両者が納得するまで話し合えばよいだろうと思った。しかし、それをしようにも、何ら経営の実態が不明だということが大きな問題だった。決算数値も分からなかったし、試合ごとの入場者数すら、ろくに把握していないようだった。当時のプロ野球では、入場者数は、“ざる”把握で、かつ、“水増し”発表が常だった。「本日の観客は25000人です。」などという、やけに切りのいい、どう見てもそんなにいないだろうという数字でアナウンスが行われていた。このような状態で「今のままではやっていけない」と言われても、説得力はないし、危機感もまったく伝わってこない。不信感が募るばかりなのだ。
後に、Jリーグのやり方を見ていて、選手やサポーターにも同じ危機感を共有し、緊張感のある経営を行うために、オープンネスが極めて重要で効果的だということがよく分かった。観客動員数は、「48721人です。」と一桁まで実数発表している。良くても悪くても、本当の数字を出すことが、クラブの経営努力を生み、周囲の協力も得られるのだ。
Jリーグでは、クラブの経理内容をリーグに提出することを規約で決めている。各チームが親会社からどれだけもらっているか、選手にどれだけ出しているか、全部分かるようにしている。従って、リーグから各クラブに対して、選手の年俸が収入に対して多すぎるとか少なすぎるといった指摘までできるようにしている。常に危機感が薄れないように、周囲とも共有し、そして、何かあった際には、オープンに話し合える仕組みを整えているということだ。
このように、川淵氏は、折に触れて「プロ野球のようになってしまったらまずいぞ」という言葉を使って、周囲の危機意識を醸成していたと聞く。
ちなみに川淵氏本人は、当時は古河電工の社員だったが、サッカーの“プロ化”を進めるにあたって、籍を抜いている。選手たちをプロという立場に追い込む以上、まず上に立つ自分を追い込むのは当然と考えたのだろう。
周囲の危機意識を醸成する最も有効な方法は、やはり、上に立つ人間が行動で示すことかもしれない。