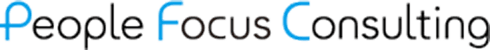コラム
2011.05.09(月) コラム
サッカーから学ぶ組織開発・人材開発 5:日本人を指導する-部活とスポーツ
【サッカーから学ぶ組織開発・人材開発(松村卓朗)】
第5回:日本人を指導する-部活とスポーツ
W杯を通じて考えさせられたことの1つに、「日本人を指導する」ということがあった。
普段私は、研修等で多くの人を指導したり教えたりする(何かを伝え、何かに気づいてもらい、何かを実践に活かしてもらう)ことを生業としているが、ことさら“日本人を”指導することについて深く考えたことはなかった。これまで、指導する対象が日本人であることは大前提だったし、日本人の指導の仕方を外国人の場合と比較する必要を感じたこともなかった。しかし、最近は研修やワークショップの参加者に外国人が混じることが少なからずあり、またグローバルに関連したテーマでの取組みでは、日本人が陥りがちな傾向を意識しながら指導することが求められることが増えているので、この機会に一度まとめておきたい。
2010年のW杯での岡田監督は、日本サッカー史上様々な革命的なことに取り組んだと述べてきたが、「日本人を指導する」ということにおいてもこれまでの監督のやり方からの転換を図っている。
岡田が指導者として目指す理想のサッカーは、「選手たちが目を輝かせて、ピッチの上で活き活きと躍動するようなサッカー」というものだった。にもかかわらず、Jリーグの監督時代にずっと抱えていた悩みは、選手が監督の“ロボット”と化してしまうことだった。「どこかやらされている感があり、自主性や主体性を引き出すことは簡単ではなかった」らしい。
例えば、選手にある指示をしたら、チームが負けているにも関わらず、「俺は監督の言う通りのことをやっていますよ」という顔をして、ベンチをちらちら見てアピールしてきたと言う。チームを勝利に導くために自らが今何をすべきかを考えることよりも、監督の指示に従うことを優先させる、そんな選手を自分の指導が作ってしまっていたのか、と愕然としたこともあったという。Jリーグで優勝を積み重ねたところで、選手の主体性や闘争心を最大限まで引き出すことは出来なかった。それが、岡田をしばらく監督業から遠ざけていた最大の理由だったと語っている。
監督がやれ、と言うことは従順にやるが、言われたことしかやらない。W杯に向けても、これが、世界と戦っていくチームにするために、日本人を指導する上で、最大のチャレンジだったと岡田は語る。「ここに敵が二人いたらね、ボールを持っている方に必ず味方一人がディフェンスに行きますよね。敵がもう一人いてもそこに行ってはいけないんで、カバーリングのポジションに下がれとボクは言う。でも、ボールを持つ敵がおどおどしていてパスを出さなそうならそこに行けばいい。敵が逃げたら2人で行く。これは選手が判断する。ボクはココが正しいポジションだと言う。しかし『監督に言われたからココにいました』、これでは選手じゃない。この傾向が日本人は外国人よりちょっと多い。」(「カンブリア宮殿」(テレビ東京))
そもそも、こうした傾向は何が招いているのか。根本的に、日本ではサッカーを“学校”でやるから、自由でないのではないか。自主性や主体性が発揮されにくいのではないか。というのが私の仮説だ。ちなみに、学校単位でスポーツをやるのは、日米韓くらいだと聞いたことがある。日本でも最近は学校ではなくクラブチームの出身者が増えてはいるが、指導者がいて教わっているなら本質は同じだ。元来世界では、サッカーは教えてもらうものではないのだ。“遊び”なのだ。
このことを私に気づかせてくれたのはセルジオ越後という人だ。世間では、口うるさい辛口のサッカー評論家くらいにしか思われていないようだが、彼は東京オリンピックの時にブラジル代表候補に選出されたほどの人物だ。1972年に来日後、日本の実業団でもプレイした。他のブラジル人選手同様、帰化して日本代表になってくれるよう頼まれたが、「自分は中身はブラジル人だから」と取り合わなかった、幻の史上最高の日本代表選手だ。
しかし、サッカーでの実績そのものよりも、実はその後の行動にこそ頭が下がる。彼は、手弁当で「さわやかサッカー教室」を開き、北は北海道から南は沖縄まで全国津々浦々を回り、少年サッカーの指導普及に努める。1年間に数十回2万人を越える参加者のサッカー教室を30年にわたって続けてきた。歴代の日本代表選手は、ほとんどすべてが少年時代にセルジオ越後に指導してもらったことがあるという話だから、その貢献たるやサッカー界の誰も及ぶものではない。
しかし、セルジオ越後は、「私は教えたのでは決してない」と言う。サッカーの楽しさを伝えたにすぎないと言う。そもそもサッカーは教えられるものではないとも言う。ブラジルでは、サッカーは、日本で言えばドッジボールの感覚らしい。確かに私もドッジボールなら、学校で誰かに教わった記憶はない。クラブに入るのでもなく、給食を速攻で腹に入れて昼休みをフルに使って、夜も暗くなるまで、夢中になって“遊んだ”。次の日の昼休みの勝負の作戦を勝手に立て、自分なりに工夫して技を磨いた。いや、サッカーだって最初私が始めた頃はこの感覚だったと思うが、部活になってやっているうちに、いつしか“遊び”の感覚はなくなってしまった。誰に強制されるものでもなく、自分のペースとテーストで勝手に創意工夫を楽しむといった感覚は削ぎ落とされてしまった。
セルジオ越後によれば、ブラジルでは、“遊び”から始まったサッカーは、“部活”にはならずに、“スポーツ”になるのだという。“部活”と“スポーツ”は大きく違う。例えば、スポーツには「補欠」という概念はない。一人ひとりが主役で、自分の興味とレベルに応じてやるものだ。部活では1校1チームでやっているから「補欠」という概念が生じてしまうのだ。あるいは、部活では小6と中1で断絶がある。この断絶は、学校教育でサッカーをやっている日本の特徴だとも言う。
そして何より、スポーツの本質は、エンジョイするという考え方だ。エンジョイするものだから、一人ひとり楽しみ方が異なる。エンジョイしようとする中で様々なものを自ら学びとっていく。もっともっとエンジョイしようとして成長もしていく。こういう感覚が、「選手たちが目を輝かせて、ピッチの上で活き活きと躍動するようなサッカー」には、最も必要だったのではないだろうか。
オシム前監督が急病で倒れて、急遽日本代表監督に就任した際、岡田は、日本代表チームにフィロソフィーを掲げた。チームフィロソフィーの1つ目に掲げ、最も大事と言ったのが、「Enjoy:状況を常に楽しめ」だった。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
選手によく話すんですけど、究極のエンジョイってのは、自分の責任でリスクを冒すことなんです。要するに、監督が「ココだ」と言ってる。でも「俺はココだ」。これで成功した時にこんなに楽しいことはないんですよ。
ギャンブルでね、自分のなけなしの金を賭けてるから、無くなったら大変だ、勝ったらこれで何を買おうかという喜びがあるわけですよね。スポーツはお金賭けないでできるギャンブル。そこが本当の楽しみなはず。最高に面白いところだぞと。自分の裁量でやるから、心の底から気持ちの高ぶりや落胆を味わえる。言われたことをこなすだけじゃ面白くもクソもないだろうという言い方をするんですけど。
でもリスクを冒して失敗したらオレは怒るぞと言いますけどね。だからリスクなんですよ、怒られるからリスク。日本の選手は「ミスしてもいいから」と言ったら、リスクを冒してチャレンジをするんです。でも「リスクを冒して失敗しても褒めよう」なんてリスクじゃなくなるんですよ、それは。
(出所:「カンブリア宮殿」(テレビ東京))
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
日本人は言われたことはすぐできる。そしてすべてやろうともする。だから外国人監督はとてもびっくりする。しかし、そこから先、自由にやっていいよと言われると、とたんにできなくなる。だから外国人監督はまたまたびっくりする、といったことが言われてきた。
岡田監督は、この次元から脱却する指導が必要だと考えた。指導者が教え込んで選手という器に何かを詰め込む指導を止めた。選手が持っているものを自らが楽しみチャレンジしながら最大限引き出せるような指導を試みた。大げさに言えば、“部活”から“スポーツ”への転換を図ったと表現できよう。その際のキーワードは、「エンジョイ」だった。遊びから始まったサッカーの本質を抉る言葉だ。
そして、指導する際、真にエンジョイできるようにするには、「ミスをするな」と言ってはいけない。言った途端に、我々日本人はミスをしないようにリスクを負わなくなるきらいがある。だから、「リスクを冒せ」とチャレンジを促す。でも、促されたり許されたから冒すのではリスクではない。自分の裁量で勝手にリスクを冒さなければ真のエンジョイにつながらない。勝手にリスクを負ったのだから、失敗したら指導者は本当に叱る。リスクからスリルを奪ってはだめなのだ。リスクを冒すことそのものを自ら勝手に楽しめるように指導できないと意味がないのだ。
もしかすると、リスクを伴った真のエンジョイは、スポーツではなく部活で育った我々日本人に最も欠けているものかもしれないと思った。企業の教育や指導の現場でも、真面目に学ばせようとすればするほど、動きを窮屈にさせてしまっていることがあるのではないか。あるいは、チャレンジを促すことを推奨して、逆にリスクを冒す楽しみを本人から奪ってしまっていることがあるのではないか。「日本人を指導する」ということに携わる者は、こうした難しくも挑戦しがいのあるハンドリングが求められることを常に肝に銘じ、“部活”ではなく、“スポーツ”の世界に導くことを志したい。
そして、何より、「目を輝かせて、ピッチの上で活き活きと躍動するような」本当に楽しい経験を味わわせることを、常に指導の理想像として目指したい。セルジオ越後は、「日本のサッカー界には、私も含めどんな指導者もかなわない最高の指導者がいた。自分が数十年かかってやったこと(即ち、サッカーを教えるのではなく、サッカーの楽しさを伝えること)を、『キャプテン翼』という漫画はたった1~2年でやってしまった」、と笑いながら話していた。その話を聞いて、私も翼君が繰り出す数々の技とプレイを真似しようと、夢中になって遊んでいた、サッカーをとてもエンジョイしていた少年時代を思い出した。
サッカーから学ぶ組織開発・人材開発 4:グローバルに活躍する人材を育てる(下)
サッカーから学ぶ組織開発・人材開発 6:日本のスタイルの追求